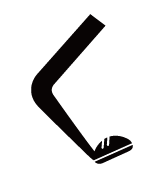何かがキラりと光って、視界の端っこに入ってくる。
視線をやると、そこには懐かしい気分になる何かや、ちょっとくすぐったい感じがする何かがみつかる。
なんとはなしに商店街を歩くと、ところどころに記憶を揺り動かすものが散りばめられていることに気づく。
通りを歩けば、思い出のかけらが其処此処に埋まっている。
だから商店街を歩くのは楽しい。
どの商店街にも、懐かしいあの日と今とちょっとの明日が混ざっている。
「あぁ、今日もいい日だなあ。」と、のんびり期待もせず。てくてくと行くのがいい。
それが商店街の歩きかたではないだろうか。
幼少時代、僕の家は魚屋を営んでいた。
46歳中年の幼少の話で恐縮なのだが、そんなことで、もちろん周りにはまだ八百屋や金物屋や酒屋があり、商店街はそこに住む皆んなの生活を支える小さい街として動いていた。
八百屋にはその時代に珍しく、上から吊るしたお釣り入れの籠がまだ現役で活躍しており、酒屋はケースごとビールを家に届けてくれていた。
酒屋のおじさんが持ってくるビールケースがうらやましくて、祖父に懇願して(父親は相手にしてくれなかったので)
三ツ矢サイダーをケースで買ってもらえることになったのは、小学4年のときだ。 三ツ矢サイダーのケースをカタカタ揺らしながらおじさんが初めて玄関に運んできた様子をみて、ついに自分も大人の一員になったような気になり、なんともいえない興奮に浸っていたことを覚えている。
三ツ矢サイダーのケースをカタカタ揺らしながらおじさんが初めて玄関に運んできた様子をみて、ついに自分も大人の一員になったような気になり、なんともいえない興奮に浸っていたことを覚えている。
さらに話はずれるが、クラスには三ツ矢サイダー派とキリンレモン派がありお互い罵りあったものだが、他の地域でもやはりあったのだろうか。
キリンレモン派の友達の家で初めて飲んだとき、その甘くない味わいと強めの炭酸が、その子のちょっとスカしたイメージに重なり、なんとなく負けた気がした。キリンレモンと聞くと思い出す。
家の周囲はそんな商店街中心の世界だったが、世の中にはコンビニエンスストアが定着し始める時代でもあった。
かゆいところに手が届く商品ラインナップに、24時間または深夜までやっている営業スタイル。
どこをとっても近所の商店街のどの店でも立ち向かえないほどの充実度、洗練度に、僕らちびっこたちがやられない訳がない。
三軒先には文房具屋があるのに、7分かかるコンビニまで消しゴムを買いに行くほど、コンビニは魅力で満ち溢れていた。
その頃以来コンビニは、あって当然、行って当然という感覚となり、暮らしの中心にあるはずだった商店街は、いつの間にか僕の中から消えていった。
それからの僕の人生は、まわりに歩調を合わせるがごとく、自身も進学して、愉快な学生生活を謳歌しているふりをしながら学生時代を過ごし、なんとか希望するマスコミの世界に潜りこんで、なんとか仕事をするようになった。
それからしばらく経ったある日。
5月のゆったりとした晴れた日の夕方、翌日の撮影のために前入りした出張先で(前入りだから)時間を持て余していたので部屋から外を眺めてみると、程近い場所に商店街の古ぼけたアーケードがみえた。
晩飯までにはまだ時間があるし、それなら冷やかしがてら行ってみるか、となんの気なしに向かうことにした。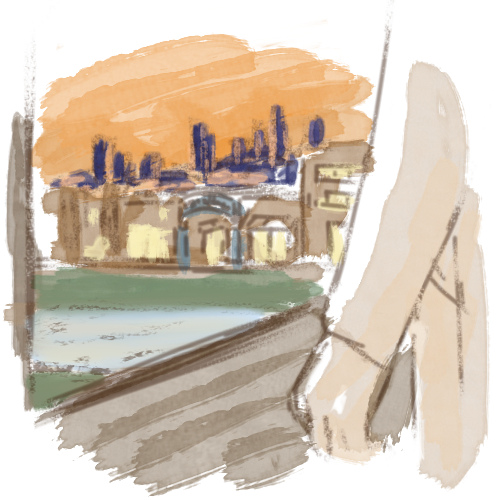 なにか興味をそそるものがあったわけでもない。
なにか興味をそそるものがあったわけでもない。
たとえばすれ違った人の顔をよく見たくなって二度見返すようなものだったと思う。
実際にアーケードの前に立ったときは、その佇まいに、なんでわざわざ来てしまったんだろうと、ちょっと自分の思いつきにがっかりした。
それでもせっかく来たのだからと思って商店街の中を進む。
すると自分の目に入ってきたのは、思い出すこともなかった昔の友人たちとの再会のような、ちょっと嬉しいような恥ずかしいような気持ちにさせられる店々だった。
埃まみれの看板、古ぼけたスチール製の棚に飾られた靴がひっそりと売られている靴屋。
誰が着るのか見当もつかないデザインの女物のセーターが飾られている洋品店。
そこだけ陽が差しているような活気のある八百屋。
買い食いしないほうが不自然なぐらいのできたてコロッケを売る精肉店。
そんな中、シャッターが閉まっているお店にも、その看板からは当時の様子が感じられ、新しく仲間入りしたような洒落たカフェは、それでもその商店街がもつ独特の気配をすでにうっすら纏っていた。
この優しくほんのり温もる気配こそ、長い時間かけて積み重なってできたものであり、商店街だけが紡ぎ出すことのできる魅力であることを僕は実感した。
そして、僕は40歳を過ぎていた。
この体験をして僕は、意識から消えていた商店街というものに、再び興味をもつようになった。
発展している商店街もあれば、変わらない商店街もあれば、寂れていく商店街もある。
そのいずれにも街の営みと時間が染み込んでいる。
それは、市井の人々の息遣いでもある。
僕は、そんな空気に包まれたくなると、商店街を歩く。
なんとなく、みんなと一緒に生きている気持ちになれるからかもしれない。
街歩きニスト
街てく。編集長 筒井ハジメ